鍛金とは
伝統の金属加工技法
金属を加工する金属加工技法には、大きく分けて「鍛金TANKIN」「鋳金TYUKIN」「彫金TYOUKIN」の三つがあり、それぞれの加工法が異なります。
日本に金属文化がもたらされたのは弥生時代のBC200年ごろで、多くは青銅器・銅鏡・銅鐸などの武器が多く、鋳金・鍛金によってつくらえました。
その後飛鳥時代には、仏教伝来に伴い金属工芸美術品が製作されてゆきます。
さらに鎌倉時代には、武器・武具・仏具などの金工品は装飾過多の傾向へと進んでゆきます。
江戸時代には装剣類に個性的なものが多く残されました。
彫金(ちょうきん)
文字の通り、たがね(鏨)を用いて金属を彫ること意味し、装飾(ジュエリー・アクセサリー)や仏具・家具などの飾り金具などを主に制作するための技術として使用されている。
技法としては、透かし・彫り・打ち出し・象眼などがある。
鋳金(ちゅうきん)
溶かした金属を鋳型(いがた)と呼ばれる型に流して表面を研磨するなどして仕上げる製作方法。日本では弥生時代以来の技術で、伝統的な工程は、鋳型の造型、合金の配合、鋳込、着色仕上げ等から成る。
鋳型の造型法によって、惣型(そうがた)、蝋型(ろうがた)、砂型(すながた)、込型(こめがた)等に分類され、主に、砂型が多く使われている。
鋳造(ちゅうぞう)とも言われ、それによってできた物を鋳物(いもの)と呼ばれる。
鍛金(たんきん)
金属に熱を加えて金槌で叩き、金属をのばして加工する技法。立体状にのばすことを鎚起(ついき)、打出し、鎚出などという。
絞り技法、絞り技法、絞り技法、絞り技法、これら4技法を併用した総合技法がある。
また、仕上げとして金属の表面処理(色上げ法)がある。





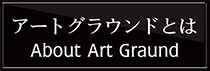



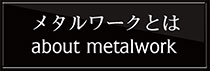
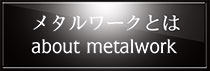
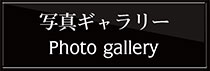
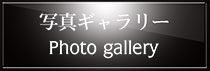








 担当者からの一言
担当者からの一言
